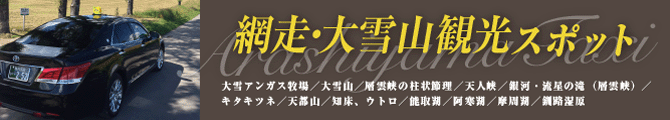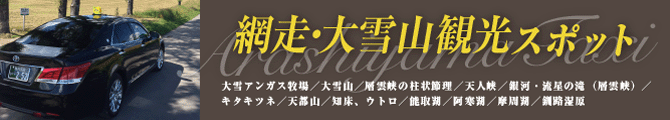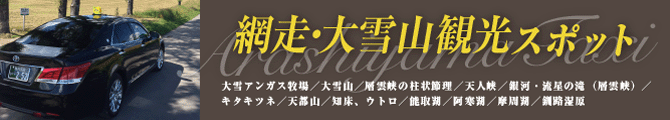 |
|
|
|
 |
|
【大雪アンガス牧場】
大雪山の麓にある広大な牧場です。晴れた日には牧場の向こうに大雪山が望め大変美しい場所。
この牧場のアンガス牛は肉牛で層雲峡などで食べることができます。
6月~7月には牧場に菜の花が一面に咲きます。その風景がこのアンガスで最も美しいとされ、必見です。
公共交通機関はないので車で行くしかありません。旭川から層雲峡にたちよる途中大自然を満喫できます。 |
|
 |
|
 |
|
【大雪山】
一つの山ではありません、「大雪山系」という呼称もしばしば使われています。大雪山系と言われる場合、広義には表大雪、北大雪、東大雪、十勝岳連峰を包含する大雪山国立公園の南北63km、東西59kmと広大な広さとなり、その面積は神奈川県とほぼ同じす
「大雪山」は本来、現在「表大雪」と呼ばれている、お鉢平を中心としたエリアを指す呼称であり、「大雪山系」がそのように使われることもあります。
国指定特別天然記念物(天然保護区域)及び国指定大雪山鳥獣保護区(面積35,534ha)に指定されています |
|
 |
|
 |
|
【層雲峡の柱状節理】
大雪山に降った雨は大雪湖に集まり、石狩川として大雪ダムから流れ出ることになります。
層雲峡は石狩川が深く谷をえぐった渓谷です。層雲峡一帯にはかつて大雪山の噴火の時に大量の灰が降り注ぎました。
その灰が固まり岩となりました。その岩を長い年月の間に石狩川が削っていったとの事。そのためその崖はもろく時々崩れることさえあります。
小函の大部分は崩落の危険があり通行止めなっています。パノラマ台はその柱状節理の上に立つことができる貴重な場所。
下から柱状節理を見あげるといつ岩が落ちてきてもおかしくないような雰囲気です。この高さを削り取った石狩川の川の流れもすごい場所。
|
|
 |
|
 |
|
【天人峡】
天人峡公営駐車場で天人峡の泉がとてもダイナミックです。
天人峡の温泉街、天人閣は開湯百年を超える老舗で、天人峡登山道や羽衣の滝・遊歩道の入口があります。
売店やレストランは宿泊者以外でも利用しやすい場所。手軽に羽衣の滝を鑑賞した後は天人閣温泉で旅の疲れを癒して下さい。
温泉の浴場入り口に、大雪山の百年水と書かれた水飲み場があり、天然の湧き水です。
お手軽大雪山のコース選びは こちらから
お問い合わせ
車種別料金一覧表表・印刷は こちらから
|
|
 |
|
 |
|
【銀河・流星の滝(層雲峡)】
絶壁・不動岩の左右から流れ落ちる滝、銀河の滝・流星の滝があります。流星の滝は断崖の間約90mの所から一本の太い線にまとまって流れ落ち・銀河の滝は約120mの高さの断崖から幾筋もの流れとなって白糸のように流れ落ちるダイナミックな景観を見せています。夏・秋・冬
の滝の写真です。日本の滝百選にも選ばれています。
|
|
 |
|
 |
|
【キタキツネ】
北海道のイメージキャラクターでもあるキタキツネは、イヌ科に属し、北半球に広く生息するアカギツネの仲間です。
北海道、南千島、サハリンに生息し、体長は60~80センチ、体重は5~10キロ。本州、四国、九州に生息するホンドギツネに比べるとやや大型で、ふっくら太く長い尾と、淡い茶色の毛が特徴です。 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
【知床、ウトロ】
斜里市街からは国道334号を知床方面に約50キロメートル移動した地点、車ではおよそ30分程度の距離です。
ウトロ温泉や知床観光船乗り場があり、温泉街が広がっています。また、カムイワッカの滝や知床五湖へ行くための国道334号の入り口にあり、国道沿いのウトロ港東側の海岸は夕日のきれいなところとして有名。町はずれにはチャシコツ岬と呼ばれるチャシ跡などがあり、2005年にはこのチャシコツ岬下のトビニタイ文化の遺跡から熊を祀った痕跡が発見され、アイヌ文化成立の経緯を解き明かす為の重要な発見として注目を集めています。知床峠を挟んだ羅臼町と共に知床観光の拠点となる場所で、2007年には道の駅うとろ・シリエトクが開設されました。
知床が世界遺産に登録されたことによる観光収益が期待されていますが、同時に観光客の増加による環境破壊も懸念との声も、厳冬期には流氷が押し寄せ、地元の観光業者による「流氷ウォーク」のツアーがあります。また、運がよければオジロワシなどの観察もできます。
満足大雪山・網走のコース選びは こちらから
お問い合わせ
車種別料金一覧表表・印刷は こちらから
|
|
 |
|
 |
|
【能取湖】
網走に真っ赤に咲くと云われているサンゴ草です。サンゴ草は、別名アッケシ草(厚岸草)はアカザ科に属する一年性草本で、
世界的にはヨーロッパ、アジア、北アメリカなどの寒帯地域に広範囲に分布します。潮汐の干満に規定される平均冠水位から、満潮水位の間の海に接する陸地や内陸に発達する塩湿地に生育する塩生植物です。
アッケシソウの茎は、濃緑色で高さ10cm~35cmくらいで円柱形で節を形成し節から枝が対生します。また、退化した燐片状の葉が節部に対生してます。
8月~9月には、茎および枝の先端部が円柱状の穂状花序をなし、葉腋のくぼみに3個の花が対となり、一つの節に6個の花器を形成します。 |
|
 |
|
 |
|
【阿寒湖】
北海道東部、釧路支庁北部にある火山性の湖水。周囲23.5キロメートル、面積12.7平方キロメートル最大深度44.8メートル、水面標高420メートル。火山活動のために形成された長径約24キロメートル、短径13キロメートルの阿寒カルデラ中央部に雄阿寒(おあかん)岳(1371メートル)が噴出したのち、周辺部の沈降と火山噴出物の堰(せき)止めによって生まれた。南東隅から阿寒川が流出する。湖岸は出入りが多く、湖中に大島、小島、ヤイタイ島、チウルイ島が浮かぶ。河口付近の水中にマリモが生息し、特別天然記念物に指定されています。
国道240号が通じ、これより分かれる241号で帯広、弟子屈と結ばれています。なお、阿寒湖は平成17年に、ラムサール条約登録湿地となりました |
|
 |
|
 |
|
【摩周湖】
阿寒国立公園内に位置する。日本の湖沼では20番目の面積規模を有する湖。
窪地に水がたまったカルデラ湖であり、アイヌ語で「キンタン・カムイ・トー(山の神の湖)」という。マシュウという名の由来は諸説あって不明です。
湖の中央に断崖の小島カムイシュ島、周囲は海抜600m前後の切り立ったカルデラ壁となっており、南東端に「カムイヌプリ(神の山)」(摩周岳・標高858m)がそびえています。湖内は阿寒国立公園の特別保護地区に指定されており、開発行為や車馬・船の乗り入れは厳しく規制されています。流入・流出河川はなく、周辺の降雨が土壌に浸透した後十分にろ過されて流入するため有機物の混入が非常に少ないとの事。 |
|
 |
|
 |
|
【釧路湿原】
釧路湿原は釧路川とその支流を抱く広大な湿原で、湿原の広さは日本最大といわれています。
タンチョウなどの水鳥をはじめ、多くの野生生物の貴重な生息地となっています。
1980年6月に、この湿原の価値が国際的に認められ、釧路湿原は日本で最初のラムサール条約登録湿地となりました。その7年後の1987年7月31日に、日本で28番目の国立公園として釧路湿原国立公園が指定されました。国立公園の面積は26,861haで、そのうちラムサール条約登録湿地は7,863haです。
釧路市、釧路町、標茶町、鶴居村の4市町村にまたがります。 |
|
 |
| |
|
|